はじめに
「風邪をひきやすい」「傷が治りにくい」などの悩みを抱えていませんか?こうした症状の一因として、体内の亜鉛が不足していることがあります。本記事では、亜鉛欠乏症と免疫機能の関係をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 亜鉛が体でどんな働きをしているか
- 亜鉛が不足すると出る主な症状
- 免疫に対してどのような影響があるか
- 欠乏の原因と、注意すべき人の特徴
- 実践できる対策と治療法の概要
専門的な用語はなるべく避け、日常の具体例を交えて説明します。自分や家族の体調管理に役立つ情報を丁寧にお伝えしますので、どうぞ気軽に読み進めてください。
亜鉛とは何か、その働き

概要
亜鉛は、体にごくわずかしか必要としない「必須微量元素」です。体内で作れないため、毎日の食事から補う必要があります。少量でも多くの大切な役割を果たします。
主な働き
- 皮膚や粘膜の健康を保ちます。傷の治りを助ける働きがあり、皮膚の再生に重要です。
- 骨や成長に関わります。子どもや若い世代の発育にも関係します。
- 味覚・嗅覚を維持します。亜鉛が不足すると味を感じにくくなることがあります。
- 生殖・ホルモンの働きを支えます。特に男性の精子形成や女性のホルモンバランスに関与します。
- さまざまな酵素の働きを助け、細胞の活動を支えます。免疫の働きにも関与します。
食事からの摂取
亜鉛は牡蠣、赤身の肉、魚介、ナッツ、豆類、全粒穀物などに含まれます。食事でバランスよくとることが大切です。
亜鉛欠乏症の概要と主な症状

亜鉛欠乏症とは
亜鉛欠乏症は、体の中の亜鉛が不足して起こる状態です。皮膚炎や口内炎、脱毛、子どもの発育障害、味覚や嗅覚の低下、免疫力の低下など、さまざまな症状を引き起こします。血液検査で血清亜鉛値が低く、臨床症状があれば「亜鉛欠乏症」、症状がない場合は「低亜鉛血症」と診断されます。
診断のポイント
- 医師は血液検査で血清亜鉛値を確認します。
- 症状の有無や程度を合わせて総合的に判断します。
- 他の栄養不足や病気が原因になっていないかも調べます。
主な症状(具体例つき)
- 皮膚症状:赤みやかさつき、湿疹が出やすくなります。手や顔に起こることが多いです。
- 口内トラブル:口内炎や舌のヒリヒリ感が出ます。食事がつらくなることがあります。
- 脱毛:髪が細く抜けやすくなります。抜け毛が急に増えたら注意です。
- 発育障害:子どもでは身長や体重の伸びが遅れることがあります。
- 味覚・嗅覚障害:食べ物の味が感じにくくなったり、匂いが鈍くなります。
- 免疫低下:風邪をひきやすく、傷の治りが遅くなります。
- 全身症状:疲れやすさ、食欲不振が続くことがあります。
症状は人によって異なります。気になる症状が続く場合は医師に相談して、血液検査で確認することをおすすめします。
亜鉛と免疫機能の関係

概要
亜鉛は免疫の働きに欠かせないミネラルです。白血球やマクロファージ、好中球、ナチュラルキラー(NK)細胞など、さまざまな免疫細胞の生成と正常な働きを支えます。亜鉛が十分にあると、体は細菌やウイルスに対して素早く反応できます。
免疫細胞への具体的な働き
- 白血球:病原体を見つけ出し攻撃する力を高めます。
- マクロファージ・好中球:異物の取り込みや消化を助け、炎症を適切にコントロールします。
- NK細胞:ウイルス感染細胞や異常細胞を直接攻撃する役割を活性化します。
これらの働きが弱まると、感染にかかりやすくなります。
アレルギーとの関連
亜鉛不足は免疫のバランスを崩し、アレルギー反応を起こしやすくします。皮膚のバリア機能が低下するとアトピー性皮膚炎や食物アレルギーのリスクが高まり、鼻炎や重度のアレルギー(アナフィラキシー)にもつながることがあります。亜鉛は炎症を抑える方向へ免疫を整える働きも持ちます。
日常でできること
亜鉛は牡蠣、赤身の肉、豆類、ナッツ、全粒穀物などに含まれます。バランスの良い食事で摂ることが基本です。サプリメントを検討する場合は、過剰摂取に注意し、医師や薬剤師に相談してください。
亜鉛欠乏による具体的な免疫低下の影響

亜鉛が不足すると、体の防御力が具体的にどう弱くなるのかをわかりやすく説明します。日常で起こりやすい問題を例にして解説します。
感染症のリスク増大
亜鉛は、細菌やウイルスと戦う免疫細胞の働きを支えます。不足すると免疫細胞の活動が落ち、感染しやすくなります。特に小児では下痢や呼吸器感染が重くなりがちです。例えば発展途上国では、下痢の治療に亜鉛を補うことで回復が早まることが報告されています。粘膜(鼻や腸の表面)のバリアも弱くなり、病原体が体内に入りやすくなります。
傷の治りが遅い
亜鉛は皮膚や粘膜を作り直す過程で必要な成分です。細胞が分裂して新しい組織を作るときに働く酵素の材料になり、不足すると切り傷や手術の傷の治りが遅くなります。結果として、傷跡が残りやすくなったり、褥瘡(床ずれ)など慢性的な傷が改善しにくくなります。
炎症・アレルギー疾患の増悪
免疫のバランスが崩れると、炎症やアレルギー反応が長引きやすくなります。アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎、食物アレルギーの症状が強くなったり、コントロールが難しくなることがあります。亜鉛は過剰な炎症を抑える働きも持つため、不足すると炎症が広がりやすくなります。
これらは日常生活に直結する問題です。次章では、亜鉛欠乏の原因について見ていきます。
亜鉛欠乏の原因
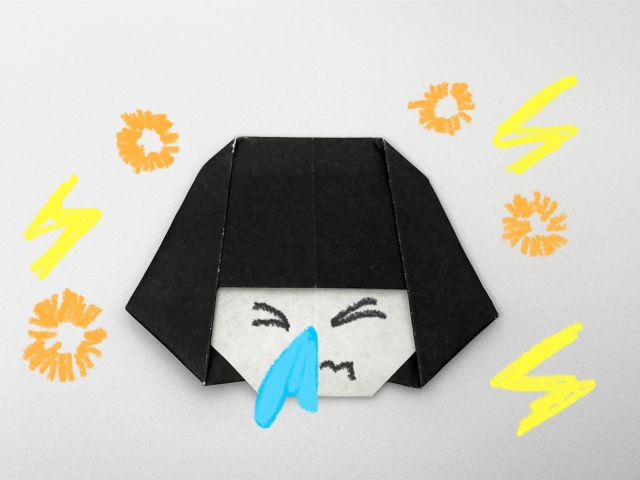
摂取不足
日々の食事で亜鉛が足りないと欠乏します。肉や魚、卵、乳製品に多く含まれますが、これらをあまり食べない偏った食事や、ダイエットでの極端な食事制限、ビーガン・菜食中心の食生活では摂取量が不足しやすいです。
吸収阻害
ある食品や成分が亜鉛の吸収を妨げます。例として、豆類や全粒穀物に含まれるフィチン酸(ぬかや玄米など)が挙げられます。お茶やコーヒーの成分も影響することがあります。薬では一部の抗菌薬やレボドパなどが吸収を妨げることがあります。
過剰な排泄・疾病
下痢や吸収不良を起こす消化器疾患(クローン病・セリアック病など)は亜鉛の吸収を低下させます。慢性腎疾患や慢性肝疾患でも貯蔵や利用が乱れることがあります。大量のアルコール摂取は尿中への排泄を増やします。
特別な状態での需要増加
妊娠・授乳期、成長期、激しい運動をする人は必要量が増えます。高齢者は食欲低下や消化吸収力の低下で不足しやすくなります。
薬剤との相互作用
利尿薬や一部の抗生物質、長期の胃酸抑制薬などが影響することがあります。服薬中に気になる場合は担当医に相談してください。
亜鉛不足になりやすい人と注意すべき症状

亜鉛不足になりやすい人
- 高齢者:食欲低下や吸収力の低下で不足しやすいです。
- 妊婦・授乳中の方:胎児や乳児へ亜鉛が優先され、自分が不足しやすくなります。
- 成長期の子ども:体が急に亜鉛を必要とします。
- ベジタリアンや偏食の方:亜鉛を多く含む肉類や魚をあまり食べない場合に注意が必要です。
- 長期のダイエットや過度の飲酒、消化吸収が悪い人:摂取量や吸収が足りなくなります。
- 腎臓病や肝疾患、慢性疾患のある方:代謝や必要量が変わることがあります。
注意すべき症状
- 味覚障害・嗅覚障害:食べ物の味が薄くなる、匂いが分かりにくくなる症状が出ます。早めに気づきやすい変化です。
- 皮膚炎・口内炎:皮膚が荒れやすく、口内に潰瘍や炎症が起きることがあります。
- 脱毛・発育障害:髪が抜けやすくなったり、子どもの成長が遅れることがあります。
- 免疫力低下・感染症にかかりやすい:風邪や皮膚感染などにかかりやすくなります。
- 傷の治りが遅い・跡が残る:切り傷や湿疹が治りにくく、跡が残りやすくなります。アトピー性皮膚炎の方に多く見られます。
見分けるポイントと受診の目安
- 複数の症状が同時に続く場合や、日常生活に支障が出る場合は受診をおすすめします。
- 医療機関では血液検査で亜鉛の状態を調べます。食事の見直しや必要ならサプリの提案を受けられます。
日常で気づいた小さな変化も大切です。早めに対処すると改善しやすくなります。
亜鉛不足の対策と治療

食事療法
まず食品からの摂取を心がけます。亜鉛を多く含むのは牡蠣、牛肉、レバー、ナッツ、卵、チーズなどです。魚介や肉に含まれる亜鉛は体に吸収されやすいため、週に数回取り入れると効果的です。全粒穀物や豆類にはフィチン酸という吸収を妨げる成分があるため、豆は戻したり発酵させたり調理法を工夫すると良いです。
サプリメントと薬物療法
医師の判断で亜鉛製剤が処方されることがあります。市販のサプリメントもありますが、用量や期間は個人差がありますので自己判断で続けず、医師や薬剤師に相談してください。過剰摂取は銅欠乏などの副作用を招くことがあります。
薬剤との相互作用に注意
一部の抗菌薬や制吐薬、レボドパなどは亜鉛吸収に影響します。服用中の薬がある場合は、医師に相談して服用の間隔を調整してください。一般に薬と亜鉛は時間をあけて摂るとよい場合が多いです。
生活上の工夫
調理でタンパク質源を意識的に加える、間食にナッツやチーズを選ぶ、バランス良く取ることを心がけます。偏食やダイエットで不足しがちな場合は特に注意してください。
受診・相談の目安
疲れやすさ、味覚障害、傷の治りが悪いなどの症状が続く場合は血液検査で亜鉛値を確認すると安心です。薬を服用中なら必ず医師に相談してください。
まとめ

本書で見てきた通り、亜鉛は免疫を支える大切な栄養素です。細胞の働きを助け、感染やアレルギーに対する抵抗力を高めます。亜鉛が不足すると、風邪をひきやすくなる、傷が治りにくい、味覚の異常が出るなど日常に支障が出ることがあります。
日常的な対策としては、バランスの良い食事で亜鉛を摂ることが基本です。具体的には、牡蠣・赤身の肉・卵・豆類・ナッツ類などを意識して取り入れてください。野菜や果物、発酵食品も消化を助け、栄養の吸収を整えます。サプリメントを使う場合は用量を守り、過剰摂取に注意してください。続けて不調がある場合は医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。
まとめると、亜鉛不足は見過ごしやすいものの、免疫と日常の健康に影響します。普段の食事を見直し、疑わしい症状が続くときは専門家に相談する習慣をつけると、健康を守りやすくなります。